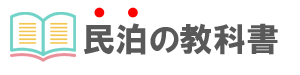「更地にすると税金が高くなるから、空き家のまま置いておいた方が良い」なんていう話を聞かれた事がある方も多いのではないでしょうか。
実際、土地に家が建っていると条件によって最大で固定資産税が1/6になる特例があります。
税金以外にも、更地にするのに多額の費用がかかる、思い出のある家を手放せない等々、さまざまな理由で空き家のまま放置されている家が増えています。
そして、放置されている空き家が増えていく中で、倒壊の恐れが出てきたり、地域の景観を著しく損ねるような空き家も増えてきたのです。
そういった状況の中で「空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」という法律が制定され、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家を行政が、調査・指導・勧告及び処分できるようになりました。
そういった空き家を民泊として使いたいという需要も今後増えてくるのではないかと思います。
今回はその「空き家対策特別措置法」とは、一体どんな法律なのかを判り易く見ていきたいと思います。
空き家対策特別措置法の目的
空き家対策特別措置法の目的として第一条に以下のように記されています。
(目的)
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

これだけ読んでもちょっと判り難いですよね。
つまり、防災・衛生の面で放っておくと危険がある、又は景観の面で生活環境に悪影響がでる可能性があるような空き家をなんとかしましょうという事です。
空き家に放火されて近所に延焼したり、害虫が大量に発生して衛生上の問題が出たり、家が老朽化して雑草も生え放題といった景観を害するような空き家をなくしていくために、持ち主に改善の勧告・命令を行い、それでも改善されない時には強制的に解体できるようになりました。
「特定空き家」って何?

空き家対策特別措置法で空き家とは、「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」と定義されています。
その中でも「特定空家」とは、以下のような空き家を指しています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
つまり、防災・衛生・環境面で特に悪影響が出る恐れがある空き家を「特定空き家」としているのです。
それでは、具体的にはどのような状態の空き家が「特定空き家」に指定されるのかを見ていきましょう。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家

- 建築物の著しい傾斜がある。
- 基礎に不同沈下がある。
- 柱が傾斜している。
- 基礎が破損又は変形している。
- 土台が腐朽又は破損している。
- 屋根が変形している。
- 屋根ふき材が剥落している。
- 壁体を貫通する穴が生じている。
- 看板、給湯設備等が転倒している。
- 屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。
- 擁壁表面に水がしみ出し、流出している。
著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家

- 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
- 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
著しく景観を損なっている状態の空き家

- 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
- 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
- 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
?周辺の生活環境のために放置することが不適切である状態の空き家

- 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
- 動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
- 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
以上のような状態を判断の基準として、特定空き家に指定するかどうかを自治体で決めることになります。
特定空き家指定から強制解体までの流れ
それでは、どういった流れで特定空き家に指定されて、その後行政からどのような指示がくるのかを見ていきましょう。
助言・指導
先ずは特定空き家と指定されそうな空き家の所有者に対して解体や修繕等の助言又は指導をおこないます。
「空き家の庭の木が道路にまで出ているのでなんとかして下さい。」というようなクレームが住民から行政に来た場合、行政は所有者に伐採をうながす助言を行います。
指導というのは、助言よりも重い行政指示ですです。
例えば、近隣住民からのクレームで行政が所有者に助言をおこなったとすると、指導はそれよりもさらに強いクレームが複数寄せられた結果の処分というイメージです。
助言や指導を受けても所有者が空き家の状態を改善しなければ、次の「勧告」を行います。
勧告
勧告は書面で行い、措置の内容は、規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内にすると規定されています。
助言・指導を何が違うのかと言うと、この勧告の時点で「特定空き家」に指定されるのです。
ですから勧告の対象になった場合、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。
このことを所有者が知らない場合もあるので、勧告時に所有者に対して固定資産税の特例の除外となる旨を示すようにガイドラインで定められています。
命令
命令になると、さらに厳しくなります。
勧告にも従わない場合、命令の実施となるのですが、その前に所有者等が公開による意見聴取の請求をすることができます。
つまり、所有者等が改善出来ない理由などを公の場で言う機会を持つことが出来ます。
もしどうしても改善出来ない理由があれば、ここで言う事が出来ます。
合理的な理由が無く勧告に従わない場合は、書面により「命令」が実施されます。
命令は行政処分で最も厳しい通達です。
命令違反に対する罰則
命令は行政処分といって、違反すると違法行為となり以下のような罰則が科せられます。
- 所有者の住所の公表
- 所有者の氏名の公表
- 50万円以下の罰金
行政代執行

命令にも従わない場合は、最後の手段の行政代執行になります。
命令には猶予期間が設けられていて、この期間内に改善が終了している必要があります。
例えば「今、改善している途中なんですよ~」と言って、実際には改善していないのに、時間稼ぎをするようなことは出来ません。
助言、指導、勧告、命令と再三の行政からの改善要求を無視してきたのですから、仕方がありません。
緊急性が高いと判断された時は、行政が所有者に代わって空き家の解体を行います。
解体費用は所有者負担
本体は所有者がするべき事を、仕方なく行政が代わって行っているわけですから、その費用は所有者に請求されます。
「そんなお金ないから払わなきゃいいや」なんていうことは許されません。
行政代執行の費用は税金債務として扱われます。
どうゆうことかと言いますと、払わない場合、所有者の同意などは一切不要で、所有者の財産を差し押さえられます。
自宅や車なども差し押さえられて競売にかけられてしまう可能性もあります。
以下に見ていきます行政代執行の例は所有者不明のため、行政で費用負担となっていますが、所有者が判る場合は所有者に請求されます。
ですから、所有者があなたと特定されている場合、空き家に対して行政代執行が行われた費用は、絶対にあなたが支払う事になると思っておいて下さい。
空き家対策特別措置法の行政代執行の実施例
2015年5月に全面施行された空き家対策特別措置法に基づいて行政代執行が行われたケースはそんなに多くはありません。
(空き家対策特別措置法以外の自治体の条例を根拠にした空き家解体の行政代執行は2015年5月以前にも行われています)
しかし施行から4ヶ月経った2015年10月時点では177の自治体が2,512軒の所有者に指導・助言を実施したというデータがあります。
このうち勧告まで行ったのは11の自治体で、命令に至った自治体はありませんでしたが、少しづつですが、確実に各自治体が空き家対策の取り組みを始めていると言えると思います。
2016年3月3日 東京都葛飾区
東京都葛飾区は3日、昨年5月に全面施行された空き家対策特別措置法に基づき、倒壊の危険性がある空き家を行政代執行で撤去する作業を始めた。
所有者は区内の高齢女性で、区は解体を求めたが応じなかった。
区によると、法施行後、所有者が判明している空き家の代執行による撤去は全国で初めて。
撤去に着手したのは、同区宝町の木造2階建ての民家で、築56年とみられる。壁の一部が剥がれ、敷地内にはごみが散乱。
区は所有者に改善するよう助言・指導、勧告、命令してきたが、聞き入れられなかったという。
区の担当者によると、所有者の女性は「以前に建て替えようと思ったが、地主と折り合わなかった」などと話している。建物の撤去は29日に完了する予定で、費用は所有者に請求する。
今回は以下の3件とは異なり、所有者が判明していて助言、指導、勧告、命令をしながらも聞き入れられなかったので強制代執行に至った初めてのケースです。
行政代執行は、助言、指導、勧告、命令と段階を踏んで、それでも改善されない場合におこなわれるので、空き家対策特別措置法が施行されたからといって、すぐに件数が増えるものでもないのかもしれません。
所有者が判明しているケースはなおさら時間がかかるのかもしれません。
施行から約10ヶ月経った時点で、所有者が判明している空き家の行政代執行が行われたと言うのは、着実に自治体の取り組みが進んでいることが分かります。
2016年02月08日 別府市
大分県別府市は8日、空き家対策特別措置法に基づき、戦後間もない頃に中国大陸からの引き揚げ者らが身を寄せた2階建ての店舗付き共同住宅「永石アパート」(同市南町)の解体に踏み切った。
所有者と連絡が取れず、築50年以上で老朽化が進み倒壊の恐れがあることから周辺住民から苦情が寄せられていた。
アパートは1947年ごろに建築されたもので、登記上の所有者は「別府海外引揚同胞自治組合」となっていたようです。
壁面が剥がれ落ちるなどしたために、2015年6月に「特定空き家」に指定されていました。
今回の解体費は約510万円ほどかかる予定で別府市が負担する方針とのころですが、土地の相続人と分担できるかも並行して交渉しているそうです。
2015年10月26日 横須賀市
対象は同市東浦賀の木造住宅で、11月末に除去作業を完了する予定。費用は市が負担する。
市から委託を受けた業者の作業員が窓を外し、植栽を伐採。周辺の道には幅が約1メートルしかない部分もあって大きな機材を使えないため、作業員は足場用のパイプを肩に担いで運んだ。
市によると、2012年10月、周辺住民から「屋根が落ちてきそうで危険だ」などの苦情が寄せられた。外壁も含めて倒壊の恐れがあり、市は放置すれば著しく危険となる恐れがある「特定空き家」と判断した。
この物件は所有者が不明なため、解体費用約150万円は市が負担することになったようです。
2015年7月 長崎県新上五島町
長崎県新上五島町が7月に約70万円をかけ、所有者不明の空き家を略式代執行で撤去していた。
1950年ごろに建てられた木造2階建ての民家が一部倒壊し、隣家や道路にがれきが散乱したため。
略式代執行による撤去は、横須賀市が10月26日に行ったものが第1号とされていたが、今回の調査で新上五島町が先だったことが判明した。
10月の横須賀市の代執行が空き家対策特別措置法に基づく略式代執行の第一号という認識が一般的ですが、実は新上五島町が第一号だったんですね。
特定空き家の解除

「特定空き家」に指定される原因となった箇所を修繕又は改善することで、特定空き家から解除されます。
自分の空き家に対して行政代執行まで行われてしまえば、その費用は必ず自分で負担することになりますので、そうならないように早めに改善をされるのが一番です。
自治体の空き家条例

空き家対策特別措置法が施行される前に、各自治体は既に条例で空き家対策を行っています。
条例では「行政代執行」まで出来るというものは少なく、「罰則」がないというものも多くあります。
それでは、大阪府、京都市、兵庫県の空き家条例をみてみましょう。(※条例は現時点のものですので、今後改正される可能性もあります。
大阪府の空き家条例
勧告・命令・公表・罰則・行政代執行
貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちを作るための条例
命令・罰則・行政代執行
勧告・命令・公表・行政代執行
「第2次美しいまちづくり推進基本計画」及び「美しいまちづくり行動計画」を策定(熊取町)
勧告・命令・公表
勧告・命令
勧告
京都府の空き家条例
勧告・命令・公表・罰則
兵庫県の空き家条例
勧告・命令・公表・行政代執行
勧告・命令・公表
勧告・公表
勧告
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今までは固定資産税の優遇処置もあって、「更地にするより空き家で放置しておいた方が良い」という認識だった方も多いと思うのですが、空き家が増え続けて社会問題となっている現在、空き家の放置に対して行政からの指導や強制的な解体ということもありえるようになってきています。
売却するにしても、賃貸するにしても、そのまま置いておくにしても、適切な管理が求められてきています。
相続などで空き家を所有した場合は、その後の管理に関しても十分気をつけなければいけない時代になっています。
そんな状況の中で、空き家の有効活用という課題は必ず出てくると思います。
社会問題となっている空き家と、新しいビジネスである民泊がうまくマッチして双方の解決策となることを期待します。