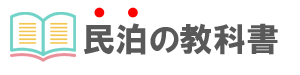第7回目の『「民泊サービス」のあり方に関する検討会』でAirbnb Japanから今後の対策に関しての発言がありました。
「グルーバルなプラットフォームが基本」としながらも、「日本のニーズに合わせた独自の取り組み」も進めていくということです。
それでは、どのような対策を予定しているのかを見ていきたいと思います。
近隣住民向け窓口の設置計画
個人宅を宿泊施設として提供している施設では、近隣住民とのトラブルが大きな問題になっています。
そこで、Airbnbで仲介している施設の近隣住民からの苦情や意見を受け付ける窓口を設置する計画があるとの発言がありました。(詳細は今後発表される予定)
民泊に関するトラブルは、騒音やゴミ出しルール無視などの近隣住民とのトラブルが多いので、この点を解決することが民泊ビジネスのポイントになると思います。
※2022年6月17日改正施行した住宅宿泊事業法では下記の通り規定されています。
(苦情等への対応)
第十条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
住宅宿泊事業法
情報シェアの仕組構築
災害や感染症など緊急時の対応としては、災害や感染症などの情報を的確にシェアできる仕組みを構築していくとのことです。
業界団体からは「一般の建物には耐震性に問題がある場合がある」「火災などに対応できない」という意見もあり、それに対しては「緊急時には警備会社が対応する例もある」との回答でした。
旅館業法では耐震性や防火性、火災報知機の設置などを義務付けていますが、個人宅にはそこまでの要求はされていないので、いざ火災や地震が起こって宿泊者がお亡くなりになられるようなことになった場合の責任を誰が取るのかという問題もあります。
また、施設に人がいない場合、避難経路への誘導などをおこなう人がいないので、スムーズに避難出来るかという心配もあります。
この防災面は近隣住民の対応と同じくらい重要だと思います。
※2022年6月17日改正施行した住宅宿泊事業法では下記の通り規定されています。
(宿泊者の安全の確保)
住宅宿泊事業法
第六条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
税の徴収代行
Airbnbは2015年10月にパリで観光税を徴収する代行サービスを開始しました。
2016年1月までの3ヶ月で約1.5億円を徴収代行したそうです。
パリと同様に「日本でも宿泊税や消費税の徴収を効率的に徴収できる体制を整えていく」との発言がありました。
ホームシェアリングに対する考え
Airbnbとしては、貸主と借主の双方が宿泊を拒むことも可能となっています。
現行の旅館業法には「引受義務」といって、予約申し込みを拒否することができません。
つまり旅館業許可を取った場合、過去に悪い評価があるからといって、部屋が空いていて貸すことが出来るのに予約を断る、ということができないです。
※生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が、令和5年7月13日に施行されました。
コロナ禍をきっかけに、正当な理由がなくマスク着用を拒む宿泊予定者や、カスタマーハラスメントを行った宿泊者の宿泊を拒むことができることとなります。
また、用途地域制限については、自宅が住居専用地域内にある場合には貸すことができなくなるため、「これはホームシェアリングとの思想とは違ってくる」とも言われていました。
投資として民泊利用するために物件を購入して貸し出しているものが「ホームシェアリング」に該当するのか分かりませんが、個人的には、ホテルなどの宿泊施設と同様の影響を周りの環境に与えるのであれば、やはり住居専用地域内での営業は規制した方が良いのではないかと思います。
※2023年10月時点、住居専用地域での民泊は各自治体の条例によって、規制されています。
まとめ
住居専用地域に家を購入した人は、静かな環境の中に住みたくて高いお金を出して家を買ったという人もいると思います。
閑静な住宅地だったところが、突然毎日知らない外国人が大声で騒ぐようなことになれば、トラブルになる可能性も高いのではないでしょうか。
宿泊施設に限らず、用途制限地域は住宅の高さや広さ、公的施設や商業施設、工業施設など非常に細かく規定されています。
それを実態がホテルなのに、「個人宅だからホームシェアリングです」という理由だけでどこでも設置して良いということになると、用途制限の意味がなくなってしまう恐れもあると思います。
周りに迷惑がかからず「三方よし」の関係を作る、という考えを前提に法改正を進めていくべきだと思います。